何故こんなことになったのだろう。
今頃は小田原城に着いて、明日にも二人揃って氏政様に拝顔していた筈だったのに。
手練を揃えたと言う、武田の透破は確かに精鋭揃いであった。
恐らく全力を尽してやっと倒せる程に。
湧き上がる不安が、駆ける足をもつれさせる。
例え自分が残ったところで、どうにもならないのは分かっていた。
程無く二人共、討ち果されたことだろう。
北条の兵が駆け付けるとなればそこは透破たるもの、敵地での引き際は心得ている筈。
だから今、己のやるべき最善の策は、麓の北条の駐屯兵に武田の侵入を知らせることなのだと、
自分に何度も言い聞かせ、思うように言うことを聞かない足を叱咤する。
そうして漸く山緑を背に翻る北条の三つ鱗紋を目にするや、小太郎は一気に跳躍して陣中に飛込んだ。
突然降って湧いた姿に兵達は一瞬敵襲かと身構えたものの、蹲るそれが満身創痍の風魔の忍と知るや、
慌てて傍へ駆け付けてきた。
「どうした!」
「――北西に一里六間、武田の透破共が這入り込んでいる」
「“共”だと? 多勢なのか、天下の小田原の膝元でなめた真似を……!」
報告に熱り立ち、すぐさま山へ向かう隊列を組み始める一団を見届けながら、
ふらりと立ち上がった小太郎を周りの兵が慌てて押し留めた。
「そんな傷でどこへ行く、待ってろ、今救護の者を呼んでやるから」
しかし小太郎はぐいとその手を除けると、再び凄まじい勢いで陣から飛び出した。

山に繰り出す兵達をあっという間に追い越し、元来た場所へと駆け戻る。
早く、早く戻らなくては。
あの人のことだから、きっと何事も無かった様な顔で透破を倒していて、
やっと戻ってきた自分を見て一言、遅い、なんて言うんだろう。
そうしたら俺は、申し訳ありません、師匠、って謝るから。謝れるから――
お願いだから、待っていてくれ、まだたった一度しか呼んでないじゃないか、
その迂闊な一声で俺はあんたの腕を奪ってしまって、この上一体何を失えというんだ、
俺の言葉が死を呼ぶというなら、俺はもう言葉を発したりはしないから、だから、どうか。
やがて山道の先がうっすらと白霞んでいるのを目にした小太郎は、その前ではたと立ち止った。
辺りは酷く静かだった。
人の声も剣戟の響きも何一つ聞こえない。
聞こえるのは己のせわしい息遣いと、破裂しそうな心臓の音のみ。
ぴりぴりと頬に貼り付く霧の粒子をぐいと拭って、小太郎は足を踏み出した。
一面踏み荒らされた地面にごろごろと転がる骸。
追いたくもないのに、目が吸い寄せられるように勝手に、それぞれの顔を確かめていく。
一人一人、仰向けになっている体を蹴起こし、その度ほっと小さな息を零しつつ、
だが同時にじわじわと胸に込み上げてくるものは不安だった。
一体、風魔はどこへ。
その時ふと、視界を見慣れた鉢金が掠めた気がして小太郎はぎくりと顔を起こした。
そうしてそちら、少し離れた岩の上に小太郎は目をやって。
やがてゆっくりとそちらに近寄っていった。
わあわあと上がる鬨の声が遠くから響いてくる。
ようやく北条の兵が到着したのだ。
背後に迫る喧騒に、つられて見上げた空はいつの間にか綺麗に晴れ上がっていて、
ああ自分は今見たこの空の色を一生忘れはしないだろう、そう思った。
風魔と共に居た日々、その終焉の日の空を。
地面に転がっていたはずの左腕は消え失せ、代わりに岩の上で、
“風魔小太郎”の証である具足と鉢金が陽に照らされ光を放っていた。
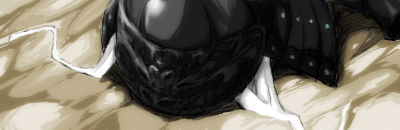
天井を微かに叩く音に振り仰ぎもせず、氏政は入りなさい、と告げた。
どうせ誰かは分かっている、今回の来訪は実に久しぶりで、氏政はそれを密かに心待ちにしていた。
前回ここに顔を出した際、風魔はしばし小田原城から離れる旨を氏政に告げていた。
次代の、継ぐ者が見付かったと。
次にお目に掛かる際にはその者も連れてくると、そう申していた。
その表情がいつになく柔らかかったのを思い出し、氏政は顎髭を撫でながら思わず顔を綻ばした。
音もなく、黒と白の装束に身を包んだ忍が降り立つ。
――現れた忍は一人だった。
その姿に氏政ははて、と首を傾げた。
身に付けている具足は確かに風魔の物、しかし何故か左腕だけは剥き出しで。
顔を覆い隠す鉢金から覗く顎の線も見慣れたものよりどこと無くほっそりとしていて。
「ふむ……名は?」
のんびりとそう問えば、しばし後に、凛とした若い声で返事が返ってきた。
「風魔、小太郎」
氏政はそうか、と頷くだけでそれ以上何も問おうとはせず、代わりに手にした急須を掲げてみせた。
「風魔よ、大儀であったな。どれ、茶でも付き合わんか?」
栄光門の上で、あの日と同じ色の空を見るたび想う。
手を伸ばせば届きそうなこの空を、あんたもどこかで眺めているのだろうか。
きっと、そうであるといい――師匠。
